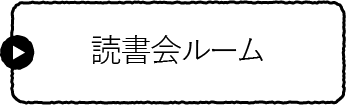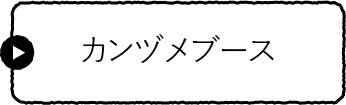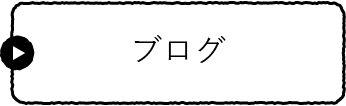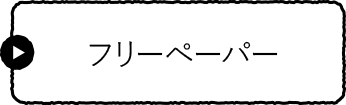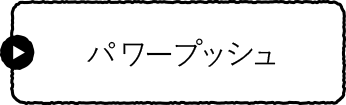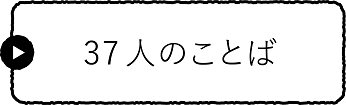『[新版]ジャパン・ディグニティ』編集者 産業編集センター・福永恵子さんからのコメント
映画『バカ塗りの娘』原作の『ジャパン・ディグニティ』は、三戸在住作家・髙森美由紀さんの一般書デビュー作であり、第1回「暮らしの小説大賞」受賞作でもあります。10年前に書かれたこの作品の編集を手がけられたのは、産業編集センターの福永恵子さんです。
デビュー作から10年間、髙森さんの伴走をされている福永さんから、「暮らしの小説大賞」受賞時のことや、映画化にあわせて刊行された『[新版]ジャパン・ディグニティ』のことなどをお伺いしました。
***
——『ジャパン・ディグニティ』の「暮らしの小説大賞」受賞から書籍化までの髙森さんとのやりとりで、印象に残っていることなどがあれば教えてください。
『ジャパン・ディグニティ』刊行の頃のことを2つ。
1つは『ジャパン・ディグニティ』が出来上がったときのご家族の反応について。「車の運転免許を取ったときのほうが喜ばれた気がする」と髙森さんから聞き、絶句しつつも「なるほど、確かにそういうものかもしれない」とやけに納得しました。
もう1つは「暮らしの小説大賞」授賞式会場で雑誌インタビューを受けた髙森さんが、開口一番「フィッシング詐欺だと思いました」と言っていたこと。「詐欺話」はその後、何度か見たり聞いたりすることになるのですが、初回は思わずそのお顔を二度見しました。でも考えてみれば、これは当然で、とても正しい反応です。
どちらも自分が謙虚に邁進するために、覚えておくべきエピソードだと思っています。
——映画化にあわせ、このたび新版が出版されました。書き下ろしで物語の6年後を描くというのは福永さんからの提案だったのでしょうか?
新版刊行にあたり、書き下ろしをお願いすることになりました。「ユウくんのお話」をリクエストしたところ、6年後の設定である「あとは漆が上手くやってくれる」を預かりました。
『ジャパン・ディグニティ』は(髙森さんの)最近の作品と比べて描写が細かいことは明らかです。ユウをキーパーソンに据えたこの書き下ろしによって、10年前と現在とがスムーズにつながりました。
——「ここに注目して読んでもらいたい」ということなど、『ジャパン・ディグニティ』の魅力を教えてください。また、映画などをきっかけにこれから『ジャパン・ディグニティ』を読む人へメッセージをお願いいたします。
事細かに描かれた伝統工芸と美也子の暮らしの混ざり具合、あるいは混ざらずに残ってしまう異物感は『ジャパン・ディグニティ』の大きな魅力です。
受賞作の単行本化にあたり髙森さんには、漆職人・清史郎(父)の思いと、漆の家である青木家の現実を、丁寧に慎重に加筆してほしいとお願いした覚えがあります。スーパーのレジ係をやめて漆を継ぎたいという美也子に、清史郎が思い、感じ、考えたのはどんなことだったのか。
映画「バカ塗りの娘」では、清史郎が「素人が!漆をなめるな!」と美也子を一喝する場面があります。そのインパクトが忘れられません。あの瞬間、私は作品のすべてが赦されように感じたのでした……。
そして、映画を観て以降、原作への印象が変わった気がします。
漆を選んだ美也子に差し伸べられる手が、他の誰でもなく清史郎のものであったこと。それはとても尊いものに思えました。10年経ってようやく気づいたことでした。
——産業編集センターさんでは髙森さんの作品を多数出版されていますが、髙森作品の魅力はどんなところにあると感じますか?
リアリティとユーモア、そこにべったり貼り付いている生活感が髙森作品の魅力です。
些細かもしれないけれど確実に存在する「日々のあれこれ」に、自分なりに向き合う作中人物たち。日常にはさりげなくもやっかいな問題というものが存在し、その問題と向き合うことは、すごく面倒くさくてしんどいことを私たちは知っています。
髙森さんが描く小説の主人公は、ダメな自分を意識しつつも、それでもやっぱりちょっと面倒なことを後回しにしてしまうタイプが多いかもしれません。職場で上司に理不尽且つ心外なことを言われた主人公は、内心で盛大にツッコミつつ、ボヤきながらも、なんだかんだと対応対処します。容赦のないツッコミに溜飲を下げ、ヨボヨボと対処する姿に切なさを覚える読者は多いはずで、かくいう私もその一人です。
一見、脆弱。でも実はかなり骨太。そのバランスの妙はきっと天然由来で、髙森さんの小説ならではの明るさとパワーの源になっていると、私は思います。
髙森さん。あっという間の10年でした。どうぞこれからも宜しくお願いします。
産業編集センター 出版部 福永恵子