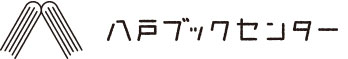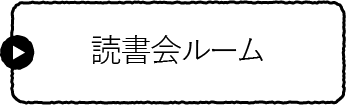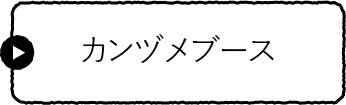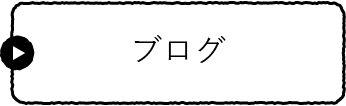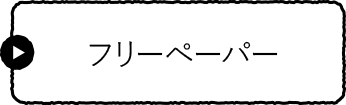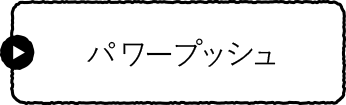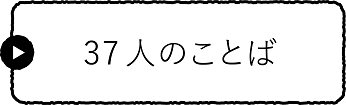「本のまち こんなまち」八戸ブックセンタースタッフ4名の座談会のようす
開催中のギャラリー展「本のまち こんなまち」のなかでご紹介している八戸ブックセンタースタッフ4名の座談会の様子を、フルバージョンでお届けします!

左から 熊澤直子、太田博子、森佳正、森花子
【ブックセンターってなに?】
太田:私は2020年に八戸に移住してきたので、ブックセンターのオープン当初のことはわからないのですが、オープンしたときの市民のみなさんの反応とかはどんな感じでしたか?
「ブックセンターってなに?」って聞かれました?
森花:それはいまだにたまに聞かれますよね(笑)
オープンの頃は、みんなここでどうしたらいいんだろう、みたいな感じがあった。
「ここは図書館?それとも本屋さん?」みたいに聞いてくれたら答えられるけど、「通ってはみたけど、結局なんだかよくわからなかった」みたいに何も言わずに帰ってしまう方もいて…。
だから私たちも「館内ツアー」を設けて、来館者のみなさんにここがどういう場所なのか説明する機会を設けました。
でも、オープンしたての頃に比べればリピーターも増えているし、この場所の楽しみ方を分かっている人は格段に増えたと思う。
珈琲を飲みながらあの本を読んでみようとか、今日はカンヅメブースで集中して書こう、とか。
みなさんがそれぞれの方法で楽しんでくれている。
森佳:そうだね、正式な視察とは別に館内ツアーをはじめたのは確かに大きかったよね。
太田:館内ツアーは私たちにとっても、お客様がどこから、何を見てここに来たのかなどをヒアリングできるいい機会だと思います。
森花:館内ツアーをご希望される方の中には、知らずに偶然来たという人もいるけれど、ブックセンターに来たくてわざわざ遠方から来てくれたっていう人も多いですよね。
ブックセンターができたから八戸に立ち寄ってみた、とか。
だから市民の方にどう受け止められているかということもあるけど、市外・県外の方に支えられてきた部分もかなりあると思う。
森佳:そう、関係人口をどんどん増やしてきた感じ。
森花:それで、逆輸入じゃないけど、市外の人に「あなたの街はいいわね」って言われたりして、だんだん市民の方も「なんか注目されているんだな…」って感じで受け入れてくれたのは良かったですね。
太田:市外から来たお客様に、「ほかに八戸のおすすめスポットありますか」とか結構聞かれたりして、夜だったらお酒も楽しめるANDBOOKS MAGAZINEとかをおすすめするんですけれど、みなさんはどんなところをおすすめしたりしますか?
森花:最近できた、ろっかく珈琲の中のわくわく書房かな。
珈琲も楽しめるしいいですよね。
森佳:新井田川を越えると、全国的にも有名な酒蔵の「八戸酒造」とかも見学できるしね。
それに、日曜日の朝だったら館鼻岸壁で朝市も開催されているし。
森花:ブックセンターのイベントは土曜日に開催することが多いから、頑張って早起きできるゲストは翌日朝市を楽しんだりすることもありますよね。
でも、酔いつぶれてしまったら難しいけれど(笑)
太田:朝市に本屋さんが出店したら面白そう。
でも、朝早いと暗くて本は読めないからあんまり売れないかな?
読書用のヘッドライトと一緒に販売するとか…(笑)
出張ブックセンターとして、いろいろなところで本を販売してみたいですよね。

【「本のまち」になるまで】
太田:八戸ブックセンターに勤めるために移住してきて、思っていたのと違うこととか、驚いたこととかありますか?
森花:私たちが来たときはまだ「本のまち」が確立していたわけじゃなくて、何にもないところから自分たちが作るぞ!っていう感じだったから、あまりギャップとかで悩んだことはないかな。
熊澤:「本のまち」になってきたなと実感するのはブックフェスのときだと思います。
最初の頃のブックフェスは、マチニワに長机も出さずにやっていて。地面に直に座って、本家の一箱古本市みたいな感じでしたよね。
森佳:どこかの国の市場、バザールみたいな感じだったね。(笑)
熊澤:そこからだんだん規模が大きくなって、参加者も増えて、色々な出版社さんが来てくれるようになりました。
市内の飲食店さんや、DJの方も参加してくれるようになって、ますます賑やかになっていったことが印象的です。
森佳:ブックセンターの開設前から一箱古本市ははっちが主催で開催していて、それを吸収してブックフェスになった感じだよね。
イベントの名前も、最初の頃は「ブックフェス」じゃなかった気がする。
熊澤:ブックセンターが開設された初年度は、まだ「一箱古本市」だったと思います。
翌年度から「ブックフェス」になったはず。
そのときは確か台風が近づいている天気だったような…。
森佳:霧雨みたいな感じの雨が降っていてね。
出店してくれた人たちは大変だったと思う。
本も濡れちゃうし。
森花:その頃はまだDJの方たちも参加していなくて、会場の音もなかったからちょっとさみしい感じになっちゃったんだよね。
森佳:それで急遽「何かしなくては!」となって、熊澤さんと2人でリポーターと撮影ディレクターみたいに各店舗にインタビューして、それをマチニワビジョンで生番組みたいに流したんだよね。
そういう経験があって、やっぱり会場には音があった方がいいと分かったので、翌年から地元で活躍するDJの人に出演をお願いしたり。
飲み物だけじゃなくて、やっぱり食べ物もあった方がいいということになって市内の飲食店さんにつないでもらったり。
8年やっているから、そのなかでさまざまな変化が目に見えてあったのがブックフェスだと思う。
太田:ブックフェス初回の大変なときから、地元の書店員さんたちは協力してくれていたんですね。
森佳:ブックセンターができる前まではやはり書店って同じ商品を売っている訳だし、どこで買うかという違いになると、どうしてもライバル関係になる。
各書店で本を販売する店員さんたちの交流ってなかなか難しいのだけど、ブックフェスの中で名物書店員さんとして、市内各書店でそれぞれのジャンルに力を入れている3人の書店員さんにはっちひろばでお話してもらったことがあって。
それはイベントだったんだけれど、そのときの様子は中高生向けの冊子にまとめてもらったりもした。
今でもお互いにエールを送り合える関係を築けたというのはやはり八戸ブックセンターが持つ「公共」の力も大きいと感じるね。
太田:八戸ブックセンターは今まで本当に多くの作家さんが応援してくれてきたけれど、書店員さんにもすごく支えられてきたという感じがしますよね。
ギャラリー展「37人のことば」のときも素敵なコメントを寄せてくださって、こういう関係があるのは特別だなと感じます。
あと、ブックセンターが開設された当初は、スタッフ主催の読書会も結構やっていましたよね?
森花:そうそう。オープンの頃はまだ読書会ルームを貸館で利用できます、と言ってもまだあまり使い方も知られていなくて、借りてくれる人があまりいなかったんです。
だから、「読書会ってこういう感じですよ」っていうのを皆さんに知ってもらうために自分たちで開催していました。
参加者がたくさん来てくれる会もあれば、1人、2人の会もあったりして(笑)
熊澤:最初の頃は本当にスタッフが頭をひねってなんとか読書会をやっていたけれど、最近は読書会ルームの予約が埋まっていることも多くてうれしいですよね。
館内ツアーをしたときに、読書団体が市内に十何件あるんですよ、ってお話ししたら県外から来たお客様にびっくりされることがあります。
太田:私も八戸に来てびっくりしたことのひとつが、読書会の文化が根付いていることです。
市読連(※八戸市読書団体連合会)も50年以上の歴史があると知ってすごく驚きました。
「読書会」っていう存在は聞いたことがあったけれど、実際に参加している方はあまり身近にいなかったから。
森花:太田さんも読書会に参加したりしていますもんね。
太田:みんなで同じ本を読んで感想を言い合ったり、ゆるいビブリオバトル形式で最近読んだ本を紹介し合ったり、毎回新鮮ですごく面白いです。
自分ではあまり選んで読まなさそうな本も、他の人におすすめされると読んでみたくなるし、新しい本との出合いのきっかけになりますよね。

↓以下、ギャラリー壁面に掲示部分です
【本を買う楽しみ】
森佳:本は出合った時に買っておかないと、次の機会がないこともあるんですよね。絶版になることも多いから。買っておいたら「積ん読」もできるしね。
森花:返却期限がある図書館と違って、自分のものにした本は読もうが読まなかろうが、手元にずっとあるのがいいよね。
太田:自分の好きな時間に好きな場所で楽しめますもんね。
森佳:ページの端を折るとか、書き込みするとかもできるし。
森花:子どもたちの場合、図書館で2 週間借りられる本を、3回借りたらもう買ってあげるのが吉、みたいのはよく聞くよ。
そう考えると、2014年から始まったマイブック推進事業で、毎年子どもたちに2,000円分のクーポンをあげてるっていうのは、「本のまち」としてすごく誇れる事業なんだけど、あんまり知られてなくて。
もっとバズってもいいと思う。
自分が本屋さんで買う、自分が買うっていうのが大事だよね。
太田:具体的に本を買う場所ってことになると、私は伊吉書院類家店で漫画を買うことが多いですね。
カネイリ番町店で文具と一緒に絵本を買うこともありますけど、花子さんはお子さんの本をどこで買いますか?
森花:ラピアの未来屋書店は、本屋さんならではの取り揃えでパズルや知育の雑貨を置いてたりして、よく行くんですよね。
熊澤さんはどこで本を買うんですか?
熊澤:私は家から近い成田本店みなと高台店に行きます。本と一緒にCDを見たりもします。
川村商店は、八戸駅をすぐ降りたところだから、ブックセンターオープンのずっと前から電車を待つ時間などに利用していました。
夜だとブックバーのANDBOOKS MAGAZINE(旧:ANDBOOKS)に行って、お酒を飲みながら雑誌を読めるし、写真展などの催しも一緒に楽しめますよね。
太田:8月には、このANDBOOKSの店主さんが中心街に古本屋GERONIMOもオープンし、昼間も古本が買えるようになりました。
店主さんのこだわりがつまった棚は眺めているだけでも楽しいのに加え、1月からは一般の方に本棚を貸す取組も始まります。
本を買うだけでなく、本を売る楽しみも経験できるのは、「本のまち」にとっても新たな楽しみかたになりそうですね。

【本の楽しみかたあれこれ】
太田:今回は、八戸市立図書館150 周年ということで、図書館や図書室についても話せたらと思います。
図書館だとカードさえ作れば誰でも借りられるし、足を運べばいつも本が読める場所があるのもいいと思います。
森佳:借りて持ち帰って読む時間って大事ですよね、たとえ一回に読み切れなかったとしても。
森花:八戸市立図書館は、借りるのはもちろんのこと、調べ物をしたい人も多いんじゃないかな。
時代小説を書いている高瀬乃一さんも、ここのヘビーユーザーで、「江戸時代の本がたくさんある図書館はすごい」っておっしゃっていました。
森佳:歴史資料を図書館が持っているっていうのが「本のまち」の歴史的な奥行きを出していると思う。
熊澤:それに、ブックセンターでお客様が探している本が、うちにも出版社にも在庫が無かった場合は、図書館にご案内したりしますよね。
森佳:「カーリル」(図書館蔵書横断検索サービス)で調べると、結構、図書館にあったりするんですよ。
太田:三浦哲郎の本などは、図書館に行くと借りられたりしますよね。
熊澤:長苗代にある風笑堂の「風わらう図書室」では、本棚オーナーとなった人に棚を貸し出していて、そこには好きな本を置いていくんだけど、そこから別の人が借りていい仕組みになっています。
それが、本から広がるコミュニケーションみたいな感じで、「借りる喜び+シェアする喜び」となっていて、すごく面白いなって思うんですよね。
太田:子どもたちにとっては、学校図書室で借りる楽しみもありますよね。
図書館には行けなくても、学校だったら毎日行くし。
そんな意味では、学校図書室を整備している学校司書さんがいる八戸は、県内でも特色のあるまちですよね。
森花:学校司書の仕事って、小・中学生が読みたいと思う本を選んだり、読んでもらえるような工夫をしているんですよね。
さらに、古い本を廃棄したりもするし、教科書に出てくる本を揃えて授業に合った本をその都度クラスに提供したり・・・本のまちにとっては、なくてはならない存在ですよね。
最初は2名から始まって、年月をかけて今は13人までになったので、市内小中学校に全校配備できている状況になりました。
ブックセンターとしては学校司書さんとは定期的な情報交換をしながら、今後もこのつながりを続けていきたいな、と。

※ここまで壁面掲載
【これからの八戸ブックセンター】
太田:ブックセンターが進めている「ブックサテライト」事業についても触れていきたいと思います。
書店や図書館以外にも本と出合える場所として、ご依頼があった場所に合わせた本棚をブックセンターが設置するというプロジェクトなんですけれども、2024年に青い森信用金庫さんは市内全店舗に設置しましたよね。
熊澤:青い森信用金庫さんは「地域とともに」というのが全店舗共通の大きなテーマではあるんですけど、同じ内容の本棚はないんです。各店舗を回って、主なお客さんの年齢層とか、地域の特徴を職員の方にヒアリングしながらその店舗に合う本を選書して本棚を作りました。
太田:あとは「本のまち」の取り組みに深く共感してくれたインテリアショップのガラージュMさんとか、シェアオフィスの風笑堂さんとか。街のなかにどんどんサテライトが増えていって、思いもよらないところで本との出合いができたらいですよね。
森佳:あとはブックスポットね。もうすでに素敵な本を揃えている場所もどんどん発掘していきたいし、市民の人に教えてもらいたいなと思う。
会社の応接室に当社の社史を揃えています、というのもブックスポットだとすると、多くの人や会社、施設が「本のまち」に関わっていると感じてもらえるんじゃないかな。
森花:でも、コロナの時期は待合室に本を置くのもダメだったけれど、最近は少し前に戻ってきている感じがしますよね。
森佳:そういうブックサテライトやブックスポットを増やしていくのも大事だし、最近感じるのは、やはりブックセンターでお客様を待っているだけじゃダメだなと。
さっきの朝市の話じゃないけど、自分たちで本を持って紹介しに行く、みたいな取り組みをした方がいいのかなと感じています。
ブックセンターが今までに作った本とかを全国各地の文学フリマとかフェスに持って行って販売したりするのもいいかもしれない。
とにかく、一歩外に出てみる、というのがこれからは必要だと思う。
あとは、ブックセンター開館10周年というのも大きな節目ではあるから、そこで何か記念の本とかを出版するのも可能性としてはありかも。
太田:いままでのギャラリー企画などで関わってくださったブックデザイナーさんとかにデザインをお願いできたら、素敵な本になりそうですよね。
あとは、カンヅメブースを利用している市民作家さんたちのなかでも、賞を受賞したり、本を出版したりする方が出てきているので、それについてもなにかまとめたり、紹介できたらいいなと思います。
森佳:カンヅメブースの利用者さんから、自分が創った創作物に対するお困りごとや相談っていうのもたまにありますよね。
出版の仕方や発表の方法については、僕たちより若い利用者さんの方が詳しいと思う。
森花:今までブックセンターがやってきたような、書く人同士で刺激を高め合えるようなイベントやワークショップは継続してやっていきたいですよね。
熊澤:ショートショート作家の田丸雅智さんによるワークショップとか、最近だと書評家の杉江松恋さんを講師にお迎えした、書く人のための講座とかは貴重な機会ですよね。
ぜひ、市民作家さんたちにはどんどん受講してもらいたいです。
太田:自分で小冊子を作るHACHINOHE ZINE CLUBのメンバーも増えてきているし、文章を書いたり、表現して発表するということがもっともっと身近に感じてもらえたらうれしいです。
あとは、サポーターズクラブというか、ずっとブックセンターを応援してくれている方たちとも何かできるといいなと思います。
熊澤:やっぱり開館10周年ってすごく大きな節目ですよね。
もっと色々考えていきたいですよね。
森佳:「本」というものの未来がどうなるかという瀬戸際で、国も動かなきゃいけなくなっている時代だし、電子書籍化の波の中で、八戸ブックセンターは「本」を取り扱う極めて特異な施設だから。
この施設が続いていくことそのものが一つの出来事となりうるようにずっと更新し続けられたらいいなと思っています。

《スタッフプロフィール》
森 佳正(もり・よしまさ)
八戸のことを全く知らずに移住して、館内の仕事の合間に地元の方々からお話を聞いたりあれやこれや調べたりして早8年。気づけば「八戸の歴史」探偵家業に片足突っ込んでいる。
森 花子(もり・はなこ)
2歳児の育児に翻弄され、息を切らしつつも、日々おもしろい絵本や児童書を探索中。おなかがすくと私のふくらはぎを噛む(痛い)猫たちが癒し。魚をさばけるようになりたい。
熊澤 直子(くまさわ・なおこ)
ブックセンターで働きつつ、古書市への出店にもハマっています。座右の書(ときどき変わる)は『寺山修司少女詩集』(角川文庫)。毎日ちいかわのことを考えています。
太田 博子(おおた・ひろこ)
八戸に住んで4年。イベントを企画したり、読書会に参加させてもらったり、忙しくも楽しい日々を過ごしています。来年は自分のZINEも作りたい…と計画中。編み物と美術と猫が好き。